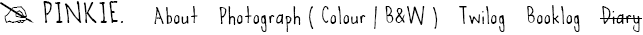最後にこの日記を更新してから、一年が経った。振り返ると、本当に一瞬、あっという間だ。
そのあいだに、わたしは卒論とプロジェクト、試験をなんとか乗り切り、無事に大学を卒業した。そして、親しんだロンドンを離れ、新しい場所へやってきた。スウェーデン・ストックホルムから電車で三時間。ダーラナ地方にある工芸学校で、今は暮らしている。
一年間。あっという間だったと言ったけれど、一年前の自分がどんなだったか、今はもう曖昧になっている。卒論を書き上げる前の自分。ここへ来る前の自分。この一年で知ったことを知る前の自分。それは、もちろんわたしなのだけど、それでいてほとんど別の人間みたいだ。
—
昨日、大学から卒業証書が届いたと、日本にいる母から連絡があった。母が送ってくれた写真の証書は、シンプルな紙切れ一枚、笑ってしまうくらいにふつうだった。名前、コースと学位、クラスが書かれただけの、大学のロゴが入った紙。飾り気のないそれは、とても、わたしが通っていた大学らしかった。
わたしはこれが欲しくて、これまでやってきたんだろうか。たぶん違う、だけどやっぱり、それはひとつの証明なのだと思う。随分長いあいだ、来る日も来る日も課題をやって、授業に出ては打ちのめされて、ときどきは出来ることが増えたとうれしくなって、その繰り返しだった。そういう、勉強することが生き甲斐だった日々の、小さな結晶。わたしがその日々で得たほんとうに大切なものはそこにはないけれど、それでも、その紙もわたしが得たもののひとつだ。
自分が卒業した大学とロンドンの街、それから何より、自分のやってきたことを愛している。誰かにとってはなんでもないことかもしれないけれど、わたしにはこれが宝で、そしてこれは一生わたしのものなのだと胸を張る。時間をかけさせてもらったことを感謝しているし、どれでもいい、わたしが得たものが、支えてくれた人たちにとっても喜ばしいものであることをひっそり願っている。
足掛け五年。泣いて笑って、特別な時間を過ごしたロンドンは、わたしのホームのひとつだ。これから何年経っても。
—
さて、わたしの現在の生活はというと、もうひとつの日記やツイッターの通り。学校の敷地内とは言え森のなかにある小屋に住んでいて、最寄りのスーパーまでは徒歩45分、坂道を下りなければいけない(つまり、帰りは上りだ)。毎日朝8時に朝食、8時40分から授業、12時から昼食、13時から16時50分までまた授業。17時から夕食をとって一日が終わるかと思いきや、課題が残っていたら21時22時まで教室で作業をしたりする。早く作業の終わった日は、趣味で何かを作ったり、勉強したりして、日記を書き、眠る。毎日が基本的にはこれの繰り返しだ。
この学校を選んだのは、これまでの勉強の自分なりの延長をここで見つけたかったからで、正直に言ってしまうとわたしは百パーセント洋裁がやりたかったわけではない(しかも織りが第一希望で、洋裁は第二希望だった)。そして実際、わたしは必要としていたものをここでちゃんと見つけられたと思っている。計算外だったのは、洋裁が思いのほか楽しいことだ。初心者もいいところなので失敗してばかりだし、そもそもこれまでやってきたことと毛色が違いすぎて戸惑いもあるけれど、もう、めちゃくちゃ楽しい。新しいことをやるってこんなに面白いものなのか、としみじみ感動してしまう。勉強を始めたばかりの言語を使って生活する感覚と、似ているかもしれない。日々、取り巻くものに名前がついていって、わかることが増えていって、どんどん焦点が合っていくような、あの感じ。
わたしはきっと、アーティストにはなれない。だけど、ここで学びたいことは無限にある。これまで得てきたものに丁寧に織り込んでいきたいものがここにはあって、だから時間が拘束されても、体力的に大変でも、やっていける。
まだまだ自分のスウェーデン語の力にはがっかりするけれど、それもこれから。来て一ヶ月で、すでに大分違うのだ。バランスの悪いやりかたではあるけれど、環境で追い込まれるというのはとてもいい。きっと今年が終わるころには見違えるようになっているに違いない、と、期待を込めて。
—
この日記を書いていない間、ほとんど毎日、メモのような日記を書きつづけた。嘘のない、純度の高いわたしは、積み重ねるとフィクションのようだ。創作が苦手なわたしも、こうして続けていけば、ひとつの物語を書けるだろうか。
何度でも同じ作業を繰り返して、そして、前へ。



わたしが通っていた中学校の裏には、大きな神社と、“糺(ただす)の森”と呼ばれる森がある。
中学生の頃は、ここにいることがただ、日常だった。 同級生と遊んだり、写生をしたり、何ともなしにぶらぶらと歩いたり。最近はここで遊んでいる中学生はあまり見かけなくなったけれど、当時は観光の人もいまほどは多くなく、休憩処もなく、自転車で走り回っていてもなにも言われないくらいだったので、本当に好きなだけここで過ごしていた。
今年の夏も、神社とその近くを流れる川へ、よく散歩にでかけた。背の高い木が並ぶ参道を歩きながら、そっと中学校の校歌を口ずさむ。“風かおる古き都 雲わたる比叡の峰は”というフレーズではじまる、ゆったりと美しい歌。入学式で聴いて、うわあ、すてきな歌、と感動したことをいまでも覚えている。
“真理(まこと)にいたる道遠くとも そびえ立つ山路たどらん”。勇ましい詞だ。
—
蜘蛛の糸のような子供時代の記憶をすり抜けて、懐かしさを振り切って、ただ美しいものを拾いあげることができるくらいには、大人になった。たぶん、そういうことだ。
神社も森も、流れる川も、比叡の峰も、昔からある喫茶店も、地元のお祭りも、この年齢になってあらためてわたしの一部になったような気がしている。唯一無二のものとして、涸れることのない、不変の故郷として。
—
大学の3回生だった頃、2ヶ月という短い期間だけ、web上でメインの日記とは別に毎日細かくメモのようなものを書いていたことがあった。できごと、食べたもの、買ったもの、読んだ本、雑感。ほぼ日手帳ですら重たく感じて続かなかったわたしがどうしてそんなことをやろうと思ったのか、今となってはもうわからない。
存在すら忘れていたその日記のことを先月ふと思い出して、しばらくぶりで読み返した。淡々とした、ただの仔細な日常の記録。けれど、大学生だった当時の何気ないあれこれが、過ぎ去った年月を感じさせない、恐ろしいほどの立体感で迫ってきた。たとえるなら初めて3Dメガネをかけたときみたいな驚きだった、本当に飛び出すやん、これ、っていう。
それはあまりにも衝撃的な体験で、その後、色々なことを考えた。これだけの情報量がごく普通の日常にあるとしたら、わたしには忘れていっていることがどれくらいあるのか、もう想像もつかない。忘れるのは健康なことだとこれまで信じてきたけれど、本当にそうだろうか、と思った。記憶なんて曖昧なもので、どんどん変わるし消えるし、掬うチャンスなんて一瞬じゃないか。
それで、twitterとこの日記の狭間で、またメモのような日記を書いてみたいと思った。日常を掬いつづけるのがいいことなのかは本当はいまでも疑問だけれど、書くことは楽しい。そして、この日々は、もう二度と戻ってはこないのだ。
http://d.hatena.ne.jp/lumi31/
“I thought the world was going to end this morning.”
“It did, man.”

わたしの新しいユリイカ棚。


両親のユリイカ棚(の、ごくごく一部)。主に70年代後半のものが並ぶ。
35年という時間がどういうものなのか、今のわたしにはまだわからない。
—
昨夏、この家は時間が止まっている、と母が言った。そんなことない、わたしはここで育って、それでいちおう大人になったじゃないのと口にしたかったけれど飲み込んだ。彼女がそう思うのなら、きっとそれがほんとうのことだ。
先月実家に帰ってきてすこし時間ができて、巨大な本棚を前にしたとき、ここだけでも時間を動かしたいと思った。それはたぶん両親のためではなくて、本のためでもなくて、わたしの意地だ。この本の集積は、これを見て育ったことは、何にもかえられない価値がある、と口に出すことで風が通ればいいと思った。これはわたしの本棚ではないけれど(とても大事なことだ、これはわたしのものじゃない)、価値を認めることを重ねて新しい時間がここに生まれればいい、とか、自己満足の極みなんだけれど、そんなことを思ったのだった。
—
がんじがらめになると、わたしにはわたしの時間があるということも忘れてしまいがちだ。ばらばらにならないよう自分自身を繋いでおくことが、どれほど難しいか。
今はただこの場所の空気に溶けるように、日々を過ごしていたい。美しいものなら、そこらじゅうにあるのだから。

眠るまえのひととき、町の灯りを想像する。家族が寝静まったあとのリビングにぺたりと座ると、扇風機の風に髪がそよぐ。BBCの臨時ニュースに釘づけになった昨夜のわたしは、もうそこにはいなかった。
まわり全部が泡のようで、立ちあがったりテレビをつけたり、本を開いたりしたら、近いところから連鎖してつぎつぎ割れてしまいそうだった。扇風機の音を聞きながら、いつか、いずれにしても、ぜんぶなくなるのに、と思う。なんのためにここにあるたくさんの機械は、ことごとく自分の偏屈な空間のそとに繋がっているんだろう。なんで知らない誰かのことが、遠い国のできごとが、現実だと思えるんだろう。見慣れた自分のからだでここにいることも泡沫の夢みたいなものなのに、吹けば消えるようなちいさな灯りのためにいちいち頭を悩ませる。わたしを被う皮膚のようなものは年を追うごとに分厚くなるどころか削れていって、ことあるごとにぴりぴり痛む。
—
けれど、いつかはなくなるもののために何かを賭けているということでいえば、皆おんなじだ。
—
本を取ろうとして、やっぱり、と手を引っ込める。ボードリヤールの遺稿集。そういえば、単純に消え去ってしまうものなど何ひとつありはしない、すべてが消滅した後に何が残るのか、それが問題だ、とこの本の冒頭にあった。消えたあとに笑いだけが残る、不思議の国のアリスに出てくるチェシャ猫、あれにすこしばかり似た状況だ、と。
いまこの瞬間に何かとんでもない、不可思議なことが起こったとしたら、わたしは自分自身を信じるだろうか、となぜかぼんやりと考えた。自分が頼りなく、透明な、ぐにゃぐにゃした物体のように思えた。
—
あてのない深夜の戯言で、わたしはなんとなく、輪郭を保っている。

The Burning House(Link)というブログがとても好きだ。自宅が燃えていたら何を持ち出すかという不吉きわまりないコンセプトだけれど、さまざまな場所に住むさまざまな人の大切なものがそこにある。“It’s a conflict between what’s practical, valuable and sentimental.” まさに、と思う。非現実的なものも、誰かに見せるために作っているだろうものもあるけれど、それでも自分(または、他人からそう見えてほしい自分)にとって大事だと各々が思っているなにかの集積というのは、なかなか壮観だ。
それで、わたしなら何を持ち出すだろうかと考えた。腕時計とコンパクトとペンダント(どれも、とても古いものだ)はわたしにとってはただの物の範疇を超えた存在で、もうお守りに近い。フィルムカメラには10年分の愛着があるので、とても置いていけない。2冊の旅行記(カール・フォン・リンネのダーラナの旅と、村上春樹『遠い太鼓』)は思い出込みで特別なもので机のうえにいつも置いてあるから、きっと10秒猶予があれば持って出てしまう。それと、眼鏡。ないと困るというか、たぶん逃げられない。あとは、ここには写っていないけれどできればiPhoneとラップトップ。データはやっぱりちょっと惜しい。ないならないで良いんだけど、きっと。
—
こうして挙げてみてわかったけれど、わたしはいざとなると実用的なものにきっと興味がない。財布やパスポートは探しもしないだろうし、データを失うとしても最悪電子機器は置いていく。高価なものも、このカメラが手持ちのものでおそらく一番なので考えない(ちなみにわたしの母はいざとなったら着物を担いで逃げると言ったので、まずは命を大切にするよう諭しておいた)。正直自分がこんなにセンチメンタルな人間だとは思わなかった。カメラとか、身につけるものとか、どう考えても鏡以外には使い道のない古いコンパクト(!)が、いちばん大切だなんて。
子供の頃、ひまわりのイヤリングや、つるりとした鉱石、太陽系惑星の情報を書き込んだノートなんかを宝箱にいれて大切にしていた。あの頃のわたしはたしかにああいうものでできていたのだ、と思う。ほかにも大切なものは沢山あって、箱になんて入りきらなくて、自分で把握すらできていなくて、それでもあの箱の中身はやっぱりわたしそのものだった気がする。うまく説明できないけどなんていうか、わたしはそういうタイプなんだろう。
大人になったいまのわたしを形づくっているのはこの小さなものたちなのかもしれないな、と、思ったり。

近くて遠い、これも、ひとつさよならをした日の写真。
—
ヨーロッパで暮らした4年のあいだ、さよならをする機会はいくらでもあった。以前よりもわかりやすく、色々な人と、色々な形でお別れをした。ときにはパーティーを開いて、ときには駅や夜のまちでハグをして、ときには授業や試験の終わりに、またね、と気軽な言葉を残して。勿論そのあと再会した人も、メッセージのやりとりをしている人もいるけれど、もう一生会えない人も沢山いるんだろう。留学生というのはとかくもう会えない別れが多くなるものだけれど、わたしの場合は特に途中で1年の留学内留学があるカリキュラムだから、毎年膨大な別れを経験することになった。
人と別れることは、必ずしも同義ではないにせよ、場所を失うことだ。場所と別れるのが先か人と別れるのが先かは場合によるけれど、ともかくその人にまつわる、付随する空間が(すくなくとも日常的には)手の届かないところにいってしまうということ。それが、わたしには辛い。あの空間にはもう戻れない、っていうのは単純な事実としていつもそこにあるものだけど、目の前で扉を閉められるようで、けっこう絶望を誘う。
だけど最近は、以前にくらべると別れに対して大仰に思わなくなった。ある種の諦念もあるし、慣れによって耐性がついたのもあるけれど、なにより、降ってくるものを少しは消化できるようになったからだ。だって望まなくても、節目じゃなくても、いつだって別れはやってくる。そのなかには多くはなくてもいつかまた、と思えるものもあって、たとえばそれが叶わなくてもう会えなかったとしても全部がなかったことにはならない(という考えかたにようやく納得がいくようになったってこと)。これを人間関係と呼べるのかはわからないけれど、それでもその、またね、の中には軽いトーンの、やわらかい手触りの希望がある。塵みたいな重さかもしれないけれど、自分から欠けてしまったあらゆる空間や人へ向かう恋しい気持ちを、わたしはそれで彩って宥めているのだった。
—
こうして自己完結したり、関係を相手に委ねることばかりしている自分をつねづね狡いとは思っているけれど(わたしは相手が自分に興味がなかったら怖いのでなかなか誰かに連絡ができない、胸を張って言うことでもないけども)、それでも受け身のわたしなりに大切にしているものがある。割り切ったり失ったり、共有したものが過去だと認めたり、糸のような関係を繋ぎとめたり、そうしながら前へいくこと。自分なりにきちんとひとりでいること。だけど、(別れには何段階もあるけれど)これ以上の別れを予感させない温度の関係が目の前にあるなら、それを大事にすること。
ヨーロッパでの生活で知り合った友人、とくに互いをひとつのチームのように感じていた学科の友人たちとの数々の別れを思うたび、須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』の最後の一節を思い出す。わたしたちはこうして理想を共有していたわけでは多分ないけれど、それでも。こんな風に別れを経験したい、こんな風に孤独でいたい、と、思うのだ。
“それぞれの心のなかにある書店が微妙に違っているのを、若い私たちは無視して、いちずに前進しようとした。その相違が、人間のだれもが、究極においては生きなければならない孤独と隣あわせで、人それぞれ自分自身の孤独を確立しないかぎり、人生は始まらないということを、すくなくとも私は、ながいこと理解できないでいた。
若い日に思い描いたコルシア・デイ・セルヴィ書店を徐々に失うことによって、私たちはすこしずつ、孤独が、かつて私たちを恐れさせたような荒野でないことを知ったように思う。”
— 須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』 232ページ
—
旅行を終えて、日本に帰ってきた。JALのマイルを使って行ったので関空発ではなく伊丹発で成田乗り継ぎ、パリまでの往復チケットだったのだけど、帰国日の成田—伊丹便が満席だったので、それをいいことに東京に寄って4日間過ごした。色々な人が時間をつくって会ってくれて、とても有難かった。ひとりでもあちこち行こうと思っていたけれど、時間いっぱいいっぱいで、神保町の古本屋さんへ行くのがやっと。けれど、よい東京滞在だった。
案外京都での生活は忙しい。思い描いていたようにいつも好きな本を読んだり、楽器を弾いたりしていられるわけではないけれど(そりゃそうか)、しばらくは必要なことをこなしながらなるべく緩やかに暮らしたい。どうだろ?
スペインでは電車でイーグル・アイ・チェリーの古いアルバムを聴いていた。邦楽では中学生の頃からずっと途切れることなく聴きつづけているアーティストって多いけれど、洋楽では彼と、カーディガンズと、ジャミロクワイくらいじゃないだろか(多分)。彼はスウェーデンの出身だけどこういう場所に似合う声だなあ、と思うと、オリーブの木ばかりの乾いた土地が馴染みのあるもののように思えた。
記憶のなかで結びついていく音楽と場所。こういうのが増えていくのは、とても幸福なことだ。

ロンドンについてひとつだけ話をするなら、
—
ロンドンには、いたるところに大小さまざまな公園がある。夏はざわざわ緑が重なり、秋は色づいた葉が公園のそとにまで舞う。冬には葉の落ちた細かな枝が、空に血管のような模様をつくる。そして春になると、あらゆる木から芽が吹き出し、これでもかと花が咲いて、公園は人でいっぱいになる。もう町じゅう皆が浮かれているんじゃないかっていうくらい人が集まって、大抵の公園が混むのだ。本を読む人、昼寝をする人、コーヒーを飲む人、友達と話をする人、犬とたわむれる人、フリスビーやボールで遊ぶ人。
ひとりで、友達と、よく散歩をしたリージェンツ・パーク。鬱蒼として飾らないハムステッド・ヒース。陽気な人たちが狭い場所にひしめき合うソーホー・スクエア。天文台を眺めながら歩くグリニッジ・パーク。いつも教室の窓から見えていたゴードン・スクエア。それから愛してやまない、丘のうえからロンドンを見渡せるプリムローズ・ヒル。特別に思っている公園は数多くある。だけどわたしにとって本当に大切なのは、“ロンドンの公園”を一括りにした幻影というか、概念のようなものなのだと思う。広がりがあって、でも強固で、無限にじんわりと熱を発するような、そういうもの。
ロンドンの公園を歩くと、その面影を目の裏に浮かべると、日常には血がかよっていることを思い出す。わたしの思う、世界を最大限美しく紐解くための文法みたいなものを、軽やかに、けれど鮮やかに、示してもらったような気持ちになる。そのことが、複雑に絡みあったかなしさや苛立ちや、口にしたくないあらゆることをすべて押し流してくれるわけではないけれど、それでも次の日を過ごすために必要なものは貰える気がする。のだ。

まあでもこうしてなかなかに重たいものを押しつけておいて何だけれど、そこに居るだけでただただ癒されるっていう、単純な感情もある。公園はまさにわたしの癒しだった、4年間ずっと(それはそれでまた別の重さがあるな、うーん)
最後の週末は風邪をひいてしまって大半の時間をベッドで過ごしたけれど、日曜の夕方にはマグカップとピクニックシートを持ってカーディガンを羽織り、家の裏にある公園に出ていった。いいお天気で、日が長い時期だからまだ太陽も高くて、結局そのまま2時間雑誌をめくったり音楽を聴いたりして過ごした。残念は残念だけども、いまはこれでよかったんじゃないかと思っている。日だまりの中のあの幸せな2時間は、ちょっと忘れがたい。
—
たった4年、ロンドンに住んだのはそのうち3年。だけど、全力で暮らしていた日々、歯がゆさにとりつかれては机に向かっていたあの日々は、わたしにとってあまりに大きい。
関東の大学に通うことが決まって京都を離れるとき、「ここからわたしがいなくなるって、どういうことなのだろう」とこの日記に書いたのを覚えている。10年以上の月日がたって、はじめてあのときと同じことを痛いくらいに考えた、そういう5月だった。

卒業を目前に控えたいま、休学することにした。
詳しい事情は省くけれどまあちょっと色々あって(言葉がたりない)、今年完走するのは無理だと判断したのだった。正直、自分で決めたとはいえしばらくは前を向く気が起こらなかったし、落ちるところまで落ちた。何より、今年の9月からこうしたいというプランが一応あって、そのための準備もすでにほとんど終わらせていたので、それが全部潰れてしまったことがかなしかった。ロンドンで勉強が続けられればよかったんだけれど、学校やビザの関係で、それもだめになった。状況は悪くなるばかりで、これまで懸命につくってきたものが空中分解してしまったような気になって、立て直しかたが本当にわからなくて、途方に暮れた。
今はようやく落ち着いてきて、とりあえず仕方ないか、といちおうは思えるようになった。こんな形で一旦ロンドンを離れることになるとは思わなかったけれど、仕方がないのだ。なんにもしなかった、できなかったわけじゃない。来年試験を受ければちゃんと卒業できるから、完走できないわけでもない。もううんざりするほど凹んだし、それをつづけたってなんの足しにもならない。前向きな言葉を持ちあげて、よろけながら歩くのだ。
—
言語をひとつ使えるようになることは、世界がまるごとひとつ増えること。すくなくともわたしにとってはずっとそうで、だからもう8年も前に、明確な、巨大な目標をたてた。その先に具体的な得たい職業とか描く未来があったっていうよりは、たくさんの世界を持って、そのあいだを自由に行き来できるひとになりたかった。
ゴールはまだ遠そうだけれどようやく自分に40点くらいはあげられるようになった今、目標が変わらないっていうこと、それがわりにふわっとしたものだっていうこと、そのためにやっぱり勉強したいなってまだ思えるってこと、けっこうええやんって思う。練習を重ねてもっと自由に泳げるようになったら自然にいくらか形になるし、ここまで来たのだから今後わたしにしかできないことだってちゃんとあるんじゃなかろうか。まあ、楽観的すぎるかもしれないけど。
ともあれ来年の春に戻ってくるまで、勉強して、リサーチして、論文を書いてとやることは山積みだ。1年が勿体ないという気持ちはまだ消えないけれど、頭のなかであれこれを落ち着かせる期間になればいいと思っている。
—
そんなわけで、6月1日にはロンドンの家を引き払っていったん京都へ帰ります。構ってくださるかた、いらっしゃいましたらどうぞよろしく。
5月は引っ越しやら何やらで忙しくなるけれど、見たいものを全部見る1ヶ月にしたい。







ほぼ1ヶ月ぶりに、カメラに入りっぱなしになっていたメモリーカードの中身を読み込んだ。最初に出てきたのは、くらくらするほど眩しい、カシという町の写真だった。
—
南仏へ行ったのは、2月の16日から20日まで。エクス=アン=プロヴァンス、マルセイユ、ル・カネ、ヴァンス。いくつかの町で、美術館を見て歩いた。そして最終日に行ったのが、この海辺のちいさな町だ。
海辺の町については、前にもここに書いたことがある。同じ南フランスのマントン、ウェールズのスランデュドゥノ、スペイン・カタルーニャ地方のシッチェス、それからスウェーデン・ゴッドランド島のヴィスビィ。去年の11月に行った、コーンウォール地方のセント・アイヴス。3年半におよぶ留学生活で、根元から折れてしまいそうなときにわたしを救ってくれたのは、いつも冗談みたいに明るくて、なにもかもが穏やかで優しい、こういう美しい町だった。そして今度も。
カシには、美術館を見に行ったわけではなかった。だから、特別なことはなにもしなかった。町をぶらぶらと歩き、教会で静かな時間を過ごし、石段に座って地中海をただ眺めた。お世辞にも美味しいとは言えない昼ごはんを食べ、文句なしに美味しいお菓子を買った。
わたしは心の底からひとりで過ごす時間が好きなのだ、寧ろなによりそれを愛しているのだ、と気がついてしまったときは、暗澹とした気持ちになったものだった。そんなの他人を傷つけるし、自分を孤独にするし、いいことないじゃないか、と思った。けれど、こういう場所でぼんやりとしてただただ癒されたりしていると、この性質もわるくないかもなと思える。遠く離れた場所に大事なものがあるから、そのうえに胡座をかいているだけかもしれないけれど。
—
日々の課題にプレゼン、それから論文(わたしのコースはなんと英語で書く卒論のほかにスウェーデン語で書く“Advanced Project”なるものがある、同じテーマは選べないので卒論を2本書かなければいけないようなものなのだ)、と慌ただしく過ごしているうちに、誕生日を迎えてまる2週間が過ぎた。あと2週間で、4年間の授業を全部終えることになる。それから論文とエッセイの執筆が佳境に入り、最後に試験。気がついたときにはきっと、もう6月になっているにちがいない。
いまは、留学生活のなかでできあがったこの自分がもうすぐいなくなってしまうかもしれないことに、いてもたってもいられないような恐ろしさを感じながら日々を過ごしている。正直論文より試験より、それがいちばん怖い(いや、卒業できなかったらどうするよって考えるとそれも相当怖いけど)。合計3年を過ごしたこの町を離れて自分がどうなるのか、わからない。想像がつかない。だって4年前の自分は、もうはるか遠くにいるのだから。
恐怖を感じないように残りのロンドンでの日々を過ごすことはきっとわたしにはできないけれど、それでも、ここでの最後はこうありたいっていうのはある。それを演じきりたいと、思っている。

先週ターナーの展示を見に行った海洋博物館。ここにも、もう春が来ている。

På tåget —電車に乗る
ぼろぼろになった本を開ける/古い切符がすべり落ちる
ただよう空気の匂い/忘れられた友人のことば/降らないはずの雪が降り/ここにはない教会の鐘が鳴る
二月がここにある/ああいう町では/いつもいつまでも二月なのだ
窓ガラスは薄氷/ビルの森に短い昼がくる/幻想と現実のあいだで/わたしはなにも失くしていない
距離をのみこんで/電車はただ走るだけだ
—
課題のために書いたスウェーデン語のものを、日本語に訳した。4年間の授業が終わろうかというこの時期に課題で詩を書かせるというのがなんともいえずうちの大学らしいのだけど、これ、ほんとうに困ってしまった。とにかく!、わたしは創作が苦手だからだ。詩を書いたりしたのは、いったい何年ぶりだろう。
だけど、やってみると書く作業は思っていたよりずっと面白かった。というのも、“日本語に訳した”と書いたけれど、正確には下書きの段階でもうスウェーデン語と日本語を行ったり来たりしていたからだ。スウェーデン語でベースを書いて、日本語で味付けして、スウェーデン語に戻って単語や構文を選び直して韻を踏んだりリズムをつけて、それをまた日本語にして表現を選び直して、ということを何度か繰り返した。意識してやったわけじゃなくなんとなくこういう作りかたになったのだけれど、ちょっと新しい景色を見れたし、ふたつの言語が自分のなかで対等じゃないからいいのかな、とも思えた。できあがった詩はそんな大層なものじゃないしやっぱり才能ないなあとも思うけれど笑、それでも母国語には遠いことばをわざわざ使うことの意味がひとつ、増えたような気がしている。だってとても楽しかったから。
“幻想と現実のあいだで/わたしはなにも失くしていない”。そうであってほしいと、持てるかぎりの希望を込めて。