26/01/2013
by lumi on 01/30/2013
ノスタルジックな町。オニャール川にかかる橋は糸のようにぴんと張って、渡る人の影まで繊細に見せていた。
—
ジローナへ行ってきた。バルセロナからは電車で1時間半なので、それほど離れていない。けれど驚くほどに、町の風景はバルセロナとは違っていた。
カテドラルは丘の高いところに建てられているので、広場のようなところから建物まで長い階段を上っていく。ファサードはバロック、側廊はゴシック。回廊などはロマネスク。ヨーロッパの大きな教会にはよくあることだけれど、膨大な時間をかけてあれこれ手が入れられているので、とにかく様式が混ざっている。それぞれ特徴のある装飾が美しく、じっくりと見れば見るほど愉しい。
このカテドラルの宝物館には、有名な天地創造のタペストリーがある。11世紀から12世紀にかけて織られたもので、世界でもそうとう古いものらしい。旧約聖書を題材に人物や動物の模様が織り込まれていたのだけど、どこかユーモラスで可愛らしかった。織られたときには鮮やかだっただろうタペストリーはもう褪せてやさしい色になっていたけれど、本当によく受け継がれてきたものだなとしみじみ眺めた。
ジローナは、折り重なる歴史と共存している町だ、と思う。色々な民族がかわるがわるやってきて戦いの場所になることも多かったらしいこの町だけれど、今でもローマ人の遺跡がわずかに残り、12世紀から15世紀にかけてのユダヤ人コミュニティの足跡がある。そしてはるか昔に建設がはじまり、その後増幅されたり壊されたり再建されたりしてきた城壁がある。いかにもカタルーニャらしい、褐色の屋根と色とりどりの壁を持つ家もたくさんある。その旧市街がやんわり核のようになって、今暮らしているひとたちの生活が広がっている(ような気がした)
地図も見ないでただ歩いていたら不意に、町を見下ろせる、なにもない場所に出た。何人かが景色に背を向け、手すりに凭れてぺたりと座っていた。きっとここのひとたちで、町なんて見慣れてるんだろう。彼らを横目に眺めたジローナの風景は、美しいというのとはちょっと違うのかもしれないけれど、
細い路地を歩きながら思い出したのは、何年も前に行ったクロアチアのシベニクという町だった。
これまで訪れてきたたくさんの町の風景は、わたしの中に複雑に絡まり合って存在している。端を引っ張ると、
ジローナに着いてまず驚いたのは、カタルーニャの旗の多さだった。バルセロナでも1年半前と比べて増えたなあと思ったけれど、ジローナはその比ではなく、どこへ行っても旗が目に入る。あとからわかったことだけれど、ジローナは特に独立派の多い町でデモが行われることもあり、市長も独立派らしい(演説では他地域との経済の格差を独立を推進する理由に挙げ、「スペインはカタルーニャから毎秒512ユーロを受け取っている」とまで言ったそうな)
州議選では独立派が過半数の議席を占めたけれどそれでも第一党の議席は予想より伸びなかった、と昨年の秋ニュースで読んだのを風になびく旗を眺めながら思い出していた。だいいちスペイン政府が認めていないかぎりは、独立を問う住民投票がすぐに出来るかといえばそうでもないんだろう。一部の旗には“CATALUNYA nou estat d’Europa”(カタルーニャ語で、「カタルーニャ、新しいヨーロッパの国」)と書いてあったけれど、本当にカタルーニャが新しい国になる日が近い将来来るんだろうか。たとえばわたしの子どもに、「まだスペインだったころのカタルーニャに行ったことがあるよ、ジローナにはたくさん旗が掲げられていたよ」なんて、いつか話したりするんだろうか。
—
あちこちのお店がシエスタに入ってしばらくした頃、朝早くからいたジローナを離れ、フィゲラスという町に行ってみることにした。フィゲラスはジローナから電車でバルセロナとは逆方向、つまりフランス国境のほうへ30分ほど行ったところにある小さな町で、目的はダリ美術館。1年半前のスペイン旅行でずいぶんダリの作品を観て以来興味が湧き、行ってみたいと思っていたのだ。
広い館内の隅から隅まで、煙みたいにもくもくと広がるダリ・ワールド。シュルレアリスム代表のように扱われるダリだけれど、それ以前になんて言うか相当エキセントリックだ。こんなの夢に出てきたらまあうなされるだろう、と思うような作品がとにかくこれでもかと並んでいた(言い過ぎ?)
正直なところわたしはあの作品群をしっかりと噛み砕くことはできないけれど、それでもダリ自身が手がけた場所であれだけの数の作品を浴びるように観るのは、心躍る体験だった。こんなに多くの作品を観てここまで印象が変わらない画家も珍しい、と思う。奇才、という言葉がしっくりくる。ダリは本当にどこまでもダリだった。
そして思いがけず、1フロアを占めていた一連の作品に釘付けになった。海のような、宇宙のような、岩のような、人間のような。境界線があいまいなのに、たしかな手触りのある、ふしぎな絵ばかりだった。作者はダリではなく、アントニ・ピショット。生まれたときからダリに接し(両親がダリとは家族ぐるみの付き合いだったらしい)、その才能を認められ、ついにはダリと共にこのフィゲラスの美術館をつくりあげることになる芸術家。ここの館長でもある。
その静かで芯の強い作品たちを1枚1枚丁寧に観ていると、この美術館がぎりぎり正気の範疇に留まっているのは彼の協力があったからじゃないかしらと思えてきた(言い過ぎ?)。もっとこの人の作品を観てみたい、と思った。ここでピショットに出会えたのは、わたしにとっておおきな出来事だった。
フィゲラスを発ったのは、夕方5時過ぎ。
遠くに雪のある山の連なりをみつけ、









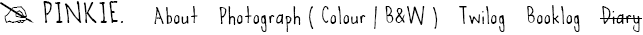
Comments are closed.