15/11/2013
by lumi on 11/15/2013
グレートブリテン島の西の果て、コーンウォール州へ行ってきた。ペンザンスという町に2泊して、3日目は朝から近くの町セント・アイヴスへ。正直海外よりよほど遠いのだけれど(ロンドンからパリやブリュッセルまでは2時間だけれど、ここまでは5時間半かかる、たとえ何もトラブルが起きなくても)、ほとんど荷物も持たずふらりと出かけていった。
何度も書いている気がするけれど、オフシーズンの避暑地、とくに海辺の小さな町が好きだ。どこへ行ってもすいているし、B&Bには信じられないくらい安く泊まれるし、海はどの季節もそれぞれきれいだし、魚介類も美味しい店を探せばいつでも美味しい。なにより、がらんとしているけれどなんともいえず穏やかで、独特の抜け感というか風通しのよさがあって、それに癒される。たまに、救われたような気さえする。
今回行ったふたつの町も、まさにそういうところだった。暫くの逃避。そういえば3日間もひとりでこんなに静かに過ごすのは(とはいえ、あちこち動いてはいるんだけれど)、ひさしぶりかもしれない。
—
ロンドン・パディントン駅を9時に出発するはずだった電車は、遅れてきたあげく、レディング駅であっさり止まって動かなくなってしまった。しかたなく次に来た電車に乗り換え(もちろん、せっかく取っていた指定席は容赦なく吹っ飛んでしまう)、西へ。ペンザンスに着いたのは16時だった。家を出てから8時間。人為的なあれこれによって、目的地は、想定していた以上に遠かった。
滞在したのは、イギリスらしい、4部屋しかない家族経営のB&Bだった。もの静かで優しいご夫婦が、美味しいお茶と朝食でもてなしてくれる。広くはないけれど行き届いたひとり用の部屋。ベッドはふかふかで大きな枕がふたつにクッション、海の見える窓があり、その枠が簡易ソファのようになっている。1日目の夜は、その窓枠に座って、暗い海を眺めながら存分に本を読んで過ごした。2日目は夕食をとっていたレストランで倒れてしまって、その後はベッドで過ごすはめになってしまったのだけれど。
ああそうか、こういう何もかもが楽しいのだ、といま書きながら振り返って思う。いいこともわるいこともあるけれど、遠出にまつわる何もかもをわたしは愛していて、それでひとりで出かけていく。使いこんだカメラをさげて、文庫本を何冊か選んで、ヘッドホンを首にかけて。
2日目はグレートブリテン島最西端の岬、Land’s endへ。ペンザンスから1時間、路線バスは細い道を走りつぎつぎ丘を越えていった。バスの二階で揺らされるがままになりながら、陸地の端の場所へ行くっていうのはなんでいつもこうなんだ、と思う。せめてもうすこし大きなバスを、もうすこし穏やかに運転してくれればいいのに。ポルトガルのロカ岬へ行ったときは酔って酔ってたいへんだったし(あれはいまだにわたし史上最悪のバス酔いであります)、ノルウェーのノールカップへ行ったときはバスのあまりの速度に曲がり角では道から落ちるんじゃないかとひやひやした。最果て訪問は、いつも忍耐とセットだ。
到着した岬は霧雨だった。そしてだいたいの天気の悪い岬がたぶんそうだけれど、台風のような風。傘をさすわけにもいかないので(宿の旦那さんにも、ぜったいに傘はささないこと、君なんてパラシュートみたいになって簡単に飛ばされてしまうよ、と忠告されていた)そのまま歩いていたら、シャワーを浴びたあとみたいになってしまった。ちょうどお昼の時間だったのでそこにあったカフェに入り、クリーム・ティーを注文して、カメラと髪を拭く。そうこうしているうちにすこし天気がよくなり、柔らかく日が差してきた。そのまましばらく、ガラス張りの暖かいカフェで荒涼とした風景をぼんやり見つめていた。
それにしても、Land’s end、きっぱりしていて情緒もある、いい名前だ、と思う。ランズエンド。
ペンザンスからセント・マイケルズ・マウント(修道院がてっぺんにある小さな島、引き潮のときは歩いて渡れるらしく、モンサンミッシェルのようだった)まで、とんでもない強風に飛ばされそうになりながら海辺を5km以上、歩いていったりもした。灰色の雲と灰色の海のなかのセント・マイケルズ・マウントはぼんやりと不気味で、風はわたしの髪を逆立てながらごうごう鳴っていて、なんだか戦いに向かうゲームの主人公にでもなったみたいで可笑しかった。
—
セント・アイヴスへ行きたかったのは、20年代にバーナード・リーチが濱田庄司を連れて帰国したときに窯を開いた町で、その頃から芸術家村として知られているところだからだった(それはそうとヨーロッパの陶芸好きの間での濱田庄司の知名度にはこれまで何度も驚かされた、ハマダという名前が外国人の口から出るというのはなかなかに不思議な感じがする)。と言ってもリーチや濱田やここで制作をした誰かのゆかりの地を巡りたかったわけでもなく、沢山の人を、とくに芸術家をひきつけたこの町が一体どういうところなのか、見てみたかったのだ、単純に。
乗り継ぎ駅のセント・アースを出発した電車はほどなくして海沿いへ出る。それからしばらく走ると、遠くの海岸線に白く光る町が見えてくる。それがセント・アイヴス。思わず、わあ、と声をあげてしまう。たまたま時間帯と天気がよかったのもあるだろうけれど、遠くから眺めるその町は、ほんとうにきらきらとしていた。
町なかをひととおり歩き、ビーチに出る。ちょうど天気が上向いてきたところで、海は青かった。犬の散歩をしている人が行き交う。立ち話をしている人もいる。やわらかい砂に沈みながら、浜をゆっくりと端から端まで歩く。
満ち潮が砂に複雑な模様をつくる。ビーチの真ん中に立ったまま、しばらく見惚れていた。
—
わたしの海への漠然とした憧れというのは自分で言うのも何だけれど中々凄まじいものがある。ひとつの大きな理由は海岸線から遠い京都市で育ったからで、もうひとつは海底二万マイルがとても好きだったからだ(たぶんわたしの人生にもっとも大きな影響を与えた本のひとつだと思う、人間はそうそう変わらない)。テートの展示は、陸地から実際に見る海というよりは、海底二万マイルを通じて感じる海に近かったと思う。触れられない、触れちゃいけない世界が横たわっているっていう、なんていうか、気配のようなもの。きっとわたしはそのぼんやりした、けれど圧倒的な何かが好きなんだ、と、思った。
イギリスの美術館では、こうして学生が絵のまえに座りこんでスケッチしたり、絵と文章の混在したメモのようなものを描いているのをよく見かける。ざっくばらんで、ぜいたくで、とってもいいと思う。
昼食をとろうとテートのカフェに入り、眼下に広がる町の美しさに驚いた。印象が、色が、ぐんと濃くなる。町というのは本当に、高いところから眺めてみないとわからない。
—
リーディングウィークはあっという間に過ぎていった。秋学期も残り半分。今年も、あと1ヶ月半だ。
海辺の町での時間はわたしを洗って、漂白してくれる。ロンドンに戻ってきてまた課題に追われても、気持ちはぴんと張ったままだ。残り少ない今年、細かなことを守りながら緩やかに生活しよう、目の前のことを確実にひとつずつやろう、と、あらためて思ったりしている。









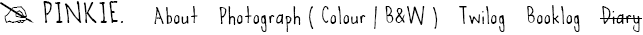
Comments are closed.