09/07/2014
by lumi on 07/9/2014
近くて遠い、これも、ひとつさよならをした日の写真。
—
ヨーロッパで暮らした4年のあいだ、さよならをする機会はいくらでもあった。以前よりもわかりやすく、色々な人と、色々な形でお別れをした。ときにはパーティーを開いて、ときには駅や夜のまちでハグをして、ときには授業や試験の終わりに、またね、と気軽な言葉を残して。勿論そのあと再会した人も、メッセージのやりとりをしている人もいるけれど、もう一生会えない人も沢山いるんだろう。留学生というのはとかくもう会えない別れが多くなるものだけれど、わたしの場合は特に途中で1年の留学内留学があるカリキュラムだから、毎年膨大な別れを経験することになった。
人と別れることは、必ずしも同義ではないにせよ、場所を失うことだ。場所と別れるのが先か人と別れるのが先かは場合によるけれど、ともかくその人にまつわる、付随する空間が(すくなくとも日常的には)手の届かないところにいってしまうということ。それが、わたしには辛い。あの空間にはもう戻れない、っていうのは単純な事実としていつもそこにあるものだけど、目の前で扉を閉められるようで、けっこう絶望を誘う。
だけど最近は、以前にくらべると別れに対して大仰に思わなくなった。ある種の諦念もあるし、慣れによって耐性がついたのもあるけれど、なにより、降ってくるものを少しは消化できるようになったからだ。だって望まなくても、節目じゃなくても、いつだって別れはやってくる。そのなかには多くはなくてもいつかまた、と思えるものもあって、たとえばそれが叶わなくてもう会えなかったとしても全部がなかったことにはならない(という考えかたにようやく納得がいくようになったってこと)。これを人間関係と呼べるのかはわからないけれど、それでもその、またね、の中には軽いトーンの、やわらかい手触りの希望がある。塵みたいな重さかもしれないけれど、自分から欠けてしまったあらゆる空間や人へ向かう恋しい気持ちを、わたしはそれで彩って宥めているのだった。
—
こうして自己完結したり、関係を相手に委ねることばかりしている自分をつねづね狡いとは思っているけれど(わたしは相手が自分に興味がなかったら怖いのでなかなか誰かに連絡ができない、胸を張って言うことでもないけども)、それでも受け身のわたしなりに大切にしているものがある。割り切ったり失ったり、共有したものが過去だと認めたり、糸のような関係を繋ぎとめたり、そうしながら前へいくこと。自分なりにきちんとひとりでいること。だけど、(別れには何段階もあるけれど)これ以上の別れを予感させない温度の関係が目の前にあるなら、それを大事にすること。
ヨーロッパでの生活で知り合った友人、とくに互いをひとつのチームのように感じていた学科の友人たちとの数々の別れを思うたび、須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』の最後の一節を思い出す。わたしたちはこうして理想を共有していたわけでは多分ないけれど、それでも。こんな風に別れを経験したい、こんな風に孤独でいたい、と、思うのだ。
“それぞれの心のなかにある書店が微妙に違っているのを、若い私たちは無視して、いちずに前進しようとした。その相違が、人間のだれもが、究極においては生きなければならない孤独と隣あわせで、人それぞれ自分自身の孤独を確立しないかぎり、人生は始まらないということを、すくなくとも私は、ながいこと理解できないでいた。
若い日に思い描いたコルシア・デイ・セルヴィ書店を徐々に失うことによって、私たちはすこしずつ、孤独が、かつて私たちを恐れさせたような荒野でないことを知ったように思う。”
— 須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』 232ページ
—
旅行を終えて、日本に帰ってきた。JALのマイルを使って行ったので関空発ではなく伊丹発で成田乗り継ぎ、パリまでの往復チケットだったのだけど、帰国日の成田—伊丹便が満席だったので、それをいいことに東京に寄って4日間過ごした。色々な人が時間をつくって会ってくれて、とても有難かった。ひとりでもあちこち行こうと思っていたけれど、時間いっぱいいっぱいで、神保町の古本屋さんへ行くのがやっと。けれど、よい東京滞在だった。
案外京都での生活は忙しい。思い描いていたようにいつも好きな本を読んだり、楽器を弾いたりしていられるわけではないけれど(そりゃそうか)、しばらくは必要なことをこなしながらなるべく緩やかに暮らしたい。どうだろ?
スペインでは電車でイーグル・アイ・チェリーの古いアルバムを聴いていた。邦楽では中学生の頃からずっと途切れることなく聴きつづけているアーティストって多いけれど、洋楽では彼と、カーディガンズと、ジャミロクワイくらいじゃないだろか(多分)。彼はスウェーデンの出身だけどこういう場所に似合う声だなあ、と思うと、オリーブの木ばかりの乾いた土地が馴染みのあるもののように思えた。
記憶のなかで結びついていく音楽と場所。こういうのが増えていくのは、とても幸福なことだ。


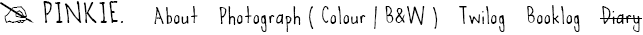
Comments are closed.