19/07/2014
by lumi on 07/19/2014
眠るまえのひととき、町の灯りを想像する。家族が寝静まったあとのリビングにぺたりと座ると、扇風機の風に髪がそよぐ。BBCの臨時ニュースに釘づけになった昨夜のわたしは、もうそこにはいなかった。
まわり全部が泡のようで、立ちあがったりテレビをつけたり、本を開いたりしたら、近いところから連鎖してつぎつぎ割れてしまいそうだった。扇風機の音を聞きながら、いつか、いずれにしても、ぜんぶなくなるのに、と思う。なんのためにここにあるたくさんの機械は、ことごとく自分の偏屈な空間のそとに繋がっているんだろう。なんで知らない誰かのことが、遠い国のできごとが、現実だと思えるんだろう。見慣れた自分のからだでここにいることも泡沫の夢みたいなものなのに、吹けば消えるようなちいさな灯りのためにいちいち頭を悩ませる。わたしを被う皮膚のようなものは年を追うごとに分厚くなるどころか削れていって、ことあるごとにぴりぴり痛む。
—
けれど、いつかはなくなるもののために何かを賭けているということでいえば、皆おんなじだ。
—
本を取ろうとして、やっぱり、と手を引っ込める。ボードリヤールの遺稿集。そういえば、単純に消え去ってしまうものなど何ひとつありはしない、すべてが消滅した後に何が残るのか、それが問題だ、とこの本の冒頭にあった。消えたあとに笑いだけが残る、不思議の国のアリスに出てくるチェシャ猫、あれにすこしばかり似た状況だ、と。
いまこの瞬間に何かとんでもない、不可思議なことが起こったとしたら、わたしは自分自身を信じるだろうか、となぜかぼんやりと考えた。自分が頼りなく、透明な、ぐにゃぐにゃした物体のように思えた。
—
あてのない深夜の戯言で、わたしはなんとなく、輪郭を保っている。


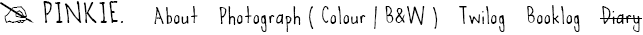
Comments are closed.